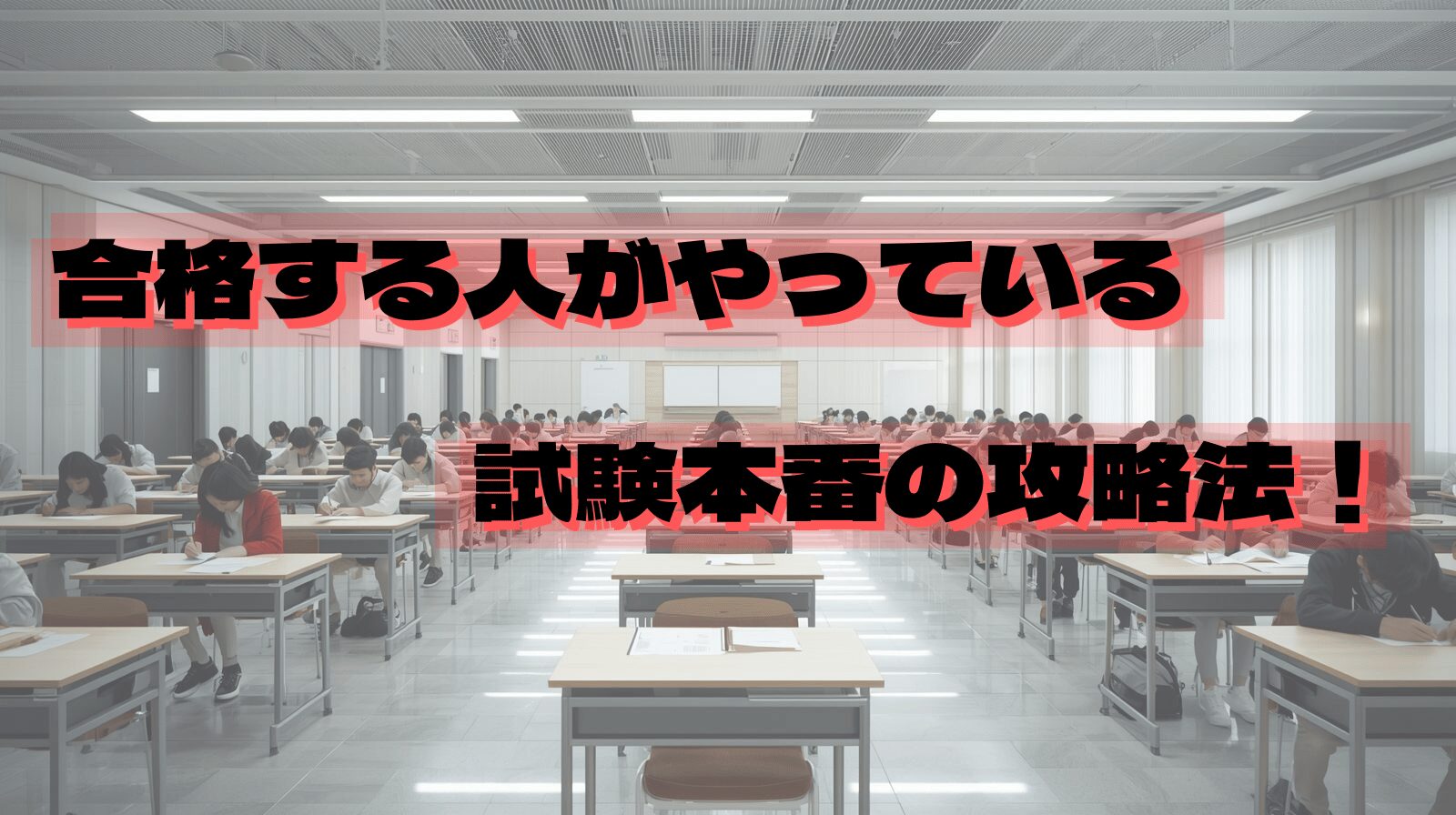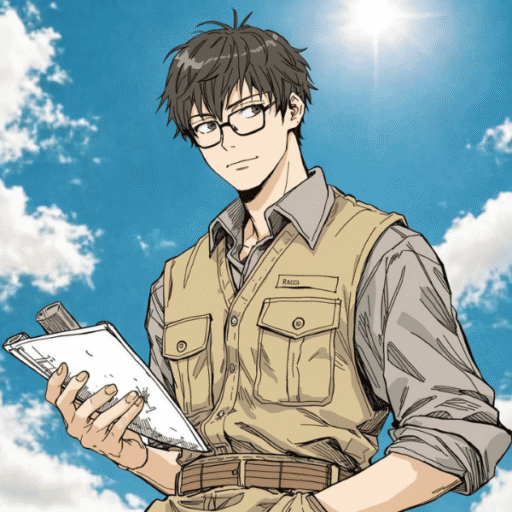「勉強はしてきたし、あとは本番!どうやって解いていこうか?」
「緊張するなぁ。大丈夫かなぁ。」
そのような不安を募ったことはありませんか?
これまで勉強方法について述べてきましたが、その努力を活かすも殺すも当日の実力次第です。緊張や時間配分ミスで、本来の実力を出しきれない人も少なくありません。
- 試験までに準備しておくべきこと
- 合格者が実際に意識している試験当日の流れ・立ち回り方
- 解答のコツ

現場監督って『段取り8割』ってよく言われますね。それは試験にも通ずると思います!余裕を持って臨めるようにしていきましょう。
前日準備
試験前日は“詰め込む日”ではなく、“整える日”です。
順に準備すべきものを見てきましょう。
持ち物の確認
まずは持ち物をチェックしましょう。前日にご覧の方は、以下のチェックリストを参考に今すぐカバンに入れちゃいましょう!
- 受験票
- 筆記用具(HBの黒鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム)
- 時計(計算機能、辞書機能、通信機能を持つ時計及び携帯電話による時計機能の使用は不可)
- 昼食
言わずもがな、『受験票』は必ず持っていってください。試験当日に会場で再発行もできるようですが、時間も取られます。万が一忘れた・紛失した際は、落ち着いて受付で再発行してくださいね。
筆記用具は、「HBの黒鉛筆又はシャープペンシル、消しゴム」という決まりがありますので、所持しているものを確認しましょう。
今後もいろんな試験で必要になると思うので、揃えておくといいかもしれませんね。

マークシートには鉛筆、筆記にはシャーペンがオススメです!
意外と多いのが、腕時計を忘れて時間配分に苦労するケースです。前述の通り、時計の機能のうち禁止されているものもありますので、事前に確認しておきましょう。
また昼食に関してですが、昼休みは約1時間あります。しかし、受験者が多いため周辺の飲食店は混雑が予想されます。コンビニも同様です。午後の部の前にもすこし見直しをしたいところなので、持参するのが好ましいと思います。

余談ですが、私は集中するためにコーヒーとラムネも持っていきました。白いダースもオススメ!
前日の勉強
前日の勉強は軽い復習だけに留め、新しい問題には手を出さないようにしましょう。
参考書や過去問、ノートを見直してください。特に苦手分野は直前に見ることで得点に繋がる可能性を高めましょう。
試験の直前に見直す用のノートを作成しておくのも1つの手段だと思います。
睡眠
睡眠不足は集中力を大きく下げるため、最低6時間は確保したいところです。
前日くらいはいつも欲に負けていた自分を思い返して、しっかり寝たほうが不安材料を減らすことにもつながります。
アロマなんか炊いてもいいと思います!

ラベンダーの香りがオススメです。心身のリラックス効果があるみたいですよ。
試験会場・交通手段
まずは、受験票に記載されている試験会場を確認してください。
受験が2回目以上の方は、前回までと同様の試験会場だと思っていると危険です。必ずしも同様の試験会場になるとは限りませんので必ず確認してください。
次に、交通手段です。
自宅やホテルを何時に出ていけば余裕を持って到着するのか調べましょう。混雑が予想されますので、直前の復習時間確保のためにも試験の1時間前には到着するのがいいと思います。
また、ほとんどの人が公共交通機関を使用すると思いますが、自動車や自転車で向かわれる方は、駐車場および駐輪場の有無を確認しておきましょう。

電車やバスだと乗車中にも復習が可能なので、スキマ時間を利用して得点を確実なものにしてくださいね。
また、当日の服装も用意しておくと良いでしょう。万が一、「寝坊した!」というときでもすぐに出発できるように備えておきましょう。心の安心にもつながりますよ。
前日は「安心して眠れる状態」を作ることが、最高の準備です。
試験当日の流れ
一次検定は、午前に2時間半・午後に2時間の試験が用意されています。間に約1時間の休憩があります。各試験開始直前に試験に関する説明をされますので、それまでは自分の席等で自由に勉強ができます。(2025年現在)
二次検定は、午後に2時間45分の試験が用意されています。一次検定と同様に直前に試験に関する説明がありますので、それまでは勉強が可能です。(2025年現在)
当日は、試験開始の30分〜1時間前には会場入りしておくのが理想です。
早めに到着すれば、トイレの場所や自分の席を確認する余裕もあります。トイレも混雑してしまいますからね。
また、直前は、苦手分野を中心に過去問ノートを軽く眺める程度にして、頭を温める程度に留めましょう。ここで体力を使ってしまうと元も子もないですからね。
私は同僚が同じ試験会場だったので、軽く問題を出し合いながら試験時間を迎えました。雑談を交えながら、気楽にしていたほうが実力を発揮しやすいと思います。
緊張は誰でもするものです。そんなときは「深呼吸+背筋を伸ばす」ことで気持ちを落ち着かせましょう。
試験監督の説明中はメモを取らずに、ルールや注意点をしっかり聞く姿勢も大切です。試験が始まったら、「焦らず、1問ずつ丁寧に」を意識してください。
一次試験の解き方のコツ
一次検定は、すべて4択の選択問題で正確さが鍵となります。時間に関してはかなり余裕を持って解答できると思います。確実に取れる問題を取りこぼさないことが最優先です。
午後のB問題はすべて必須問題ですが、午前のA問題は必須問題と選択問題が存在します。
解答していく順番に関しては、1問目から順に解くも、得意分野から手をつけていくも、どちらの方法もありかと思います。

個人的には1問目から順に解いていくほうが、解ける問題を見逃す可能性やマークミスをする可能性を減らせるのでオススメですよ。
必須問題はそのまま解き進めていけばよいのですが、選択問題では違います。
重要!
選択問題は、順に見ていくことには変わりありませんが、解答してみて自信がある問題には◯、少し迷ったなという問題には△の印をしておきます。学習するうえで、選択していなかった分野の問題と選択肢には斜線をしてしまい、余計な時間をかけないようにします。
そして、◯をつけたものはそのままマークする。そして、◯の数が解答数に満たなかったら△の中からより自信のある問題を選択しマークする。
こうすることで、取れる問題を取りこぼすということを防ぐことができます。
もちろんですが、解答数とマークは必ず確認してください。正解しても減点対象となりますので注意が必要です。
例:選択しなければいけない問題数10問、◯をつけた問題8問、△をつけた問題4問、だとします。
まずは、◯の8問をマークする。そして、△の4問の中から自信のある2問を選びマークする。最後に解答数とマークの確認を行う。
特に注意したいのは、難問にこだわって時間を失うパターンです。自分がわかる印をつけておき、全体を解き終えてから見直すくらいの気持ちで構いません。落ち着いて、機械的に処理するくらいのリズムが理想です。
二次試験の解き方のコツ
経験記述
二次試験のメインと言っても過言ではないのが、『経験記述』に関する問題です。
過去に自身で経験した工事の中から1つ選び、その工事で経験したことを記述しなければいけません。
ただし、これは事前準備が可能です。毎年、「工程管理」「品質管理」「安全管理」「出来形管理」の内から出題されます。それぞれに対応できるように解答文を用意し、それを覚えておけば大丈夫です。
解答文は、1級土木施工管理技士を取得済の職場の先輩や上司に添削してもらうこと、また添削サイトなどを利用することが好ましいです。毎日忙しそうな職場の方には聞きづらいと思いますので、添削サイトの利用をおすすめします。価格もそこまで高額なわけではないですし。

毎日忙しそうにしてる職場の方には聞きづらいと思いますよね。そんな人は添削サイトの利用をおすすめします!
価格もそこまで高額なわけでもなければ、職場の人より添削に長けているので。
記述式 穴埋め問題・文章問題
経験記述が終われば、穴埋め問題や文章による記述問題が出題されます。
一次試験では、選択できましたが、二次試験はすべて記述です。だからといって気負わず、一次試験の延長だと思い、落ち着いて解いていってください。
ただ、正しい知識や専門用語が求められますので、誤字・脱字がないかをよく確認するようにしてください。凡ミスを減らすことも合格のポイントとなります。
こちらも必須問題と選択問題が存在します。
選択問題に関しては、一次試験と同様に問いていきます。
まず問題用紙に解答を記入していき、自身のある設問には◯を、自身のないものには△をつけていきます。
そして、◯の数が多い設問を解答用紙に記入します。仮に◯の数が同じであれば△をもう一度見直し、自信のある方を解答してください。
もちろん、解答を記入した箇所が正しいか、誤字・脱字がないかを時間いっぱい確認するようにしてください。
まとめ
試験当日は、これまで積み上げてきた努力を出し切る日です。焦らず、いつも通りの自分で臨めるかどうかが、最大のポイント。
そして、段取りと冷静さこそが合格者に共通する力です。余裕を持って本番を迎えられるように前日の準備を行い、試験を自分のものにしましょう!
試験本番も「現場」と同じ。準備・流れ・判断をしっかり整えて臨めば、きっと良い結果につながります。
あなたの努力が報われるよう、心から応援しています。